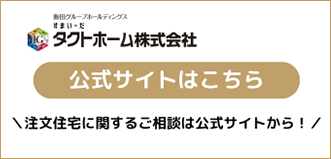家を購入すると、翌年から固定資産税が発生します。固定資産税は毎年納税しなければならない税金ですが、平屋の固定資産税は2階建てよりも高くなるといわれています。
そのため、「平屋を購入すると生活してからの負担が大きくなるのでは?」と懸念されている方も多いです。
実際のところ、平屋の固定資産税は2階建てよりも高いのでしょうか。
本記事では、平屋の固定資産税が2階建てよりも高いのかどうかや、固定資産税の計算方法、安く抑える方法を解説していきます。
平屋の固定資産税について気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
そもそも固定資産税って何?

そもそも固定資産税とは何か、皆さまはご存じでしょうか。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に対して課税される税金のことです。
毎年1月1日時点で土地や家屋を所有していることが登記簿に記帳されている人は、固定資産税の納税義務者として納税の義務を果たさなければなりません。
固定資産税の納税通知書は、毎年4~6月ごろに市町村から届きます。一般的に納税方法は、年4回に分ける方法か一括で納付する方法のどちらかを選んで納税します。
固定資産税は、土地・家屋を所有している市町村に市町村税として納税するのが原則です。
以下のようなものを所有している場合は、固定資産税の納税義務が発生します。
| 固定資産の種類 | 詳細 |
| 土地 | 田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、温泉などの鉱泉地、牧場、原野など |
| 家屋 | 住宅、店舗、発電所や変電所を含む工場、倉庫など |
| 償却資産 | 広告塔やフェンスなどの会社等(事業者)が所有する構築物、飛行機、船、車両、鉄道やトロッコなどの運搬具、パソコンや工具などの備品など |
上記のようなものを所有している場合、固定資産になります。当然ですが、戸建て住宅を購入した場合も固定資産税の対象です。
平屋の固定資産税は2階建てよりも高くなりやすい

結論からお伝えすると、平屋の固定資産税は2階建てよりも高くなりやすいです。
固定資産税は、面積の大きさに比例して金額が高くなります。平屋は2階建てよりも広い敷地がなければ希望の延床面積での建築が難しいため、必然的に広い土地が必要です。そのため、2階建てよりも固定資産税が高くなる傾向があります。
また、建物の固定資産税評価額は、立地や広さだけでなく、建材の量や施工の度合い、設備などによっても細かく変動します。同じ延床面積の建物でも、2階建てよりも平屋のほうが広い面積の屋根や壁が必要です。そのため、同じ広さでも平屋のほうが高く評価される傾向があります。
ただし、必ずしも平屋のほうが2階建てよりも固定資産税が高くなるというわけではありません。
小屋裏やロフトを利用することで延床面積を抑えていれば、その分固定資産税もかかりません。
また、土地の相場が安い郊外に建てたり、間取りを工夫して延床面積を抑えたりすることで、平屋の固定資産税の額を安く抑えられる可能性もあるでしょう。このように、少しの工夫で固定資産税を抑えることは可能となります。
平屋は固定資産税が高くなる傾向があるものの、必ずしも2階建てより高くなるわけではないことを覚えておいてください。
固定資産税の決定方法は?

固定資産税は、所有する土地や建物の資産価値をもとに決められる固定資産税評価額に対し、税率を掛けて決定されます。固定資産税評価額とは、固定資産税の額を決める際に必要な数値です。
固定資産税は家に入居後、以下の流れで決定します。
- 家屋調査
- 固定資産税評価額の決定
- 固定資産税の決定
- 納税通知書の交付
新築だと、入居後1~3カ月経過した頃に家屋調査を行う旨の連絡が届きます。
固定資産の評価を行う固定資産評価員が、家屋調査を30分程度の時間をかけて行い、固定資産税評価額が決定されます。
固定資産税評価額とは、固定資産税の額を決める際に必要な数値です。固定資産税評価額で計算された固定資産税は納税通知書に記載され、所有者に通知されます。
納税通知書を受け取った所有者は、市町村ごとに決められた納期までに納税しなければなりません。
平屋と2階建ての固定資産税を比較

では、実際に平屋と2階建ての家を例にとり、固定資産税額を比較していきましょう。
ここからは、固定資産税の計算式と計算方法、平屋と2階建てそれぞれの土地・建物の固定資産税の計算をしていきます。
固定資産税の計算式と計算方法
まず、土地と建物の固定資産税額は以下の計算式で求められます。
| 固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率) |
土地・建物の固定資産税額を算出するためには、固定資産税評価額を調べなければなりません。土地と建物の固定資産税評価額は、次の方法で市町村が算出します。
| 土地の固定資産税評価額 | 路線価×地積(m2) |
| 建物の固定資産税評価額 | 再建築価格×経年減点補正率 |
路線価は、相続税や贈与税を計算するときに使われます。国税庁の「路線価図・評価倍率表」で調べることが可能です。
建物での「再建築価格」は、新築の場合は建てるときにかかった建築費を計算に利用します。また、「経年減点補正率」は、時間の経過に伴う物理的劣化などを数値化し、評価額に反映させる重要な要素です。
これらの計算式を利用して、平屋と2階建ての固定資産税を算出していきましょう。
条件は以下に設定します。
| 【条件】 ●新築木造一戸建て(延床面積100m2) ●再建築価格 平屋:2,500万円、2階建て:2,000万円 ●建ぺい率50%、容積率100%の土地を購入 ●土地の価格(想定)5万円/m2 ●土地の固定資産税評価額(想定)購入価格の70% ●建物の固定資産税評価額(想定)再建築価格の60% ●固定資産税率1.4% |
上記の条件をもとに計算していきます。
【平屋】土地・建物の固定資産税
平屋を購入した場合の土地・建物の固定資産税を見ていきましょう。
まず、土地の広さを算出します。建ぺい率50%の土地で延床面積が100m2の家を建てるためには、少なくとも200m2の土地が必要ですので、200m2の土地を購入したと想定します。
土地の価格が5万円/m2なので、土地の購入価格は1,000万円です。
この結果から、土地の固定資産税評価額は、700万円(1,000万円×70%)となり、土地の固定資産税は、約98,000円になります。ただし、200m2以下の土地の場合、小規模用地に該当するため、1/6の軽減措置が適用されます。これにより、最終的に土地の固定資産税は、約16,300円です。
次に建物の固定資産税を算出します。
再建築価格が2,500万円なので、建物の固定資産税評価額は1,500万円(2,500万円×60%)です。そこから計算式に当てはめて固定資産税を計算すると、21万円になります。
ただし、建物にも「新築から3年間にわたり建物部分の120m2までの税額が1/2になる」という軽減措置が適用されます。その結果、建物の固定資産税は約105,000円です。
合計すると「約121,300円」がこの平屋の固定資産税となります。
【2階建て】土地・建物の固定資産税
続いて、同じ計算方法で2階建ての土地・建物の固定資産税を算出していきます。
こちらでも、土地の大きさを算出します。容積率100%の土地で延床面積100m2の2階建てを建てる場合、総二階建てであれば最低でも100m2の広さの土地であれば十分です。
この結果、土地の購入価格は500万円(5万円/m2×100m2)になり、土地の固定資産税評価額は350万円(500万円×70%)になります。この固定資産税評価額から、土地の固定資産税は、49,000円となり、軽減措置が適用されて約8,000円です。
次に建物の固定資産税を計算します。
建物の固定資産税評価額は、1,200万円(2,000万円×60%)、これをもとに固定資産税を計算すると、168,000円。軽減措置を適用すると84,000円です。
土地・建物の固定資産税を合計すると「約92,000円」となります。
この結果から、同じ延床面積でも平屋のほうが2階建てよりも税額が高いという結果になりました。
平屋の固定資産税を安く抑えるには?

必ずではありませんが、平屋は2階建てよりも固定資産税が高くなる傾向があります。
毎年納税しなければならず、その金額も決して安いものではないため、できれば固定資産税を抑えたいという方が多いでしょう。
そこで最後に、平屋の固定資産税を安く抑える方法をご紹介します。劇的に安くすることは難しいですが、ここで紹介する方法で工夫して家づくりをすることで、平屋の固定資産税を安くできる可能性があります。
木造住宅を建てる
木造住宅は、鉄筋コンクリート造や鉄骨造よりも固定資産税を抑えやすい傾向があります。建築コストも木造住宅がもっとも安く抑えられるので、建築費・固定資産税ともに金額を抑えたいなら木造住宅がおすすめです。
「木造住宅だと耐久性が不安」と考える方もいるかもしれません。しかし、木造でも耐震性・耐火性に優れた強い家を建てられます。
平屋であれば、高さが抑えられており、なおかつ基礎が広く造られているので十分な強度が期待できます。
安い土地を購入する
土地価格が安いエリアで家を建てると、固定資産税を軽減できる可能性があります。なぜなら、土地の固定資産税評価額は土地購入価格(公示価格)の70%で計算されるためです。
土地価格が安ければ、その分固定資産税評価額も安くなり、税額も安く抑えられます。
都心のほうが駅が近く、土地の利便性も高いです。しかし、土地価格が高いためその分固定資産税も高額になる傾向があります。
最近では、リモートワークが定着したことから毎日出社しないという人も増えました。そのことを考えると、都心で土地を購入して家を建てるのではなく、郊外の安いエリアで土地を購入して、土地の固定資産税を安く抑えるというのも一つの方法として検討してみてはいかがでしょうか。
建物を小さくする
建物を小さくすることで、固定資産税を安く抑えることができます。建物が小さければその分建築コストが抑えられるからです。
平屋で面積を小さくするためには、廊下やホールなどのスペースを極力減らしたり、ロフトや小屋裏などの延床面積に算入されないスペースをつくったりする方法があります。
廊下やホールの面積が少なくなれば、その分家の中での移動の効率を上げることが可能です。
また、ロフトや小屋裏は天井が低いものの、収納スペースや書斎などで十分に活用できます。
建物を小さくするための間取りの工夫を、設計士とともに計画してみましょう。
間取りをシンプルにする
間取りをシンプルにすることで、建築コストを抑えられます。
平屋の場合、正方形や長方形など凹凸の少ない家にするほうが、安いコストで建築できます。凹凸が多いと、その分使用する建材が増えるため、建築コストが上がりやすいです。
部屋数が多いのも建築コストが上がる要因です。間仕切りをできるだけ少なくして固定資産税を抑えるのも一つの方法といえるでしょう。
オプション追加を限定する
華美な装飾や住宅設備のオプションを極力減らしてシンプルに仕上げるのも、固定資産税を安く抑える一つの方法です。
室内に豪華な設備や装飾が多いと、その分建築コストも固定資産税評価額も高くなります。
家づくりの際は、優先順位を決め、オプションを追加する部分と妥協する部分を決めるようにしましょう。
長期優良住宅を建てる
長期優良住宅を建てると、新築から5年間、建物の120m2までの税額が1/2に軽減されます。
通常の新築だと3年間のところを、2年も延長されます。その分固定資産税の節約が可能です。
長期優良住宅を建てるには、耐震性・断熱性・省エネ性などさまざまな条件をクリアしなければなりません。そのため、建築コストは上がりやすいです。
しかし、長期優良住宅にすることで固定資産税の軽減措置が適用されるだけでなく、日々の光熱費の節約や地震などの災害時の安心感にもつながります。
高性能な住宅に暮らすことでランニングコストを抑えられるなら、長期的に見るとお得な家づくりの方法ともいえるでしょう。
まとめ

今回は、平屋の固定資産税について解説しました。固定資産税は、土地・建物を所有した時点で負担しなければならない税金です。毎年納税義務が発生するため、家づくりの際は固定資産税についても考え、納税時期に向けて準備をしておくことも大切でしょう。
平屋は2階建てよりも固定資産税が高くなる傾向がありますが、さまざまな工夫を凝らすことで、少しでも安く抑えることができます。
家づくりの際は、固定資産税も考慮して計画を立てることをおすすめします。平屋の家づくりで悩む方、固定資産税についてもっと知りたい方は、ぜひご相談ください。