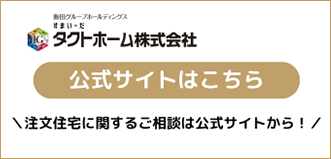借地権が付いた土地の上に家を建てることを考えたことがあるでしょうか。
こうした借地権付きの土地は、初期費用を安く抑えられるといったメリットがある一方で、建物を売却したり増改築したりするのに地主の承諾が必要になるケースがあるなど、注意しなければならないこともあります。
本記事では、借地権とはそもそもどういうものなのかといったことから、借地権付きの土地で家を建てるメリット・デメリットなど解説していきます。
Contents
借地権とは
借地権とは、「他人の土地を借りて建物を建てる権利」のことをいいます。
借地について定めた法律である借地借家法では、借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」としています。
借地権の大きな特徴は次のとおりです。
- 建物を建てるために借りた土地
- 毎月地代を支払う
- 土地の権利は貸主にある
- 無断で売却や建て替えができない
- 契約期間満了後は土地を更地で返還する
借地権では「建物の所有を目的とする」とあるため、建物を建てない駐車場を建てるための土地は該当しないのです。
土地を借りる側を借地権者、貸す側を借地権設定者や底地人と呼び、貸す側に毎月地代を支払って、土地を借りることになります。
また、土地の権利はあくまで貸す側になるため、土地を使用する際などに発生するさまざまな制限の内容をしっかり把握しておく必要があるのです。
借地権は、「地上権」「賃借権」に分けられます。
地上権とは、土地を直接的に支配できる権利のことです。
建物の建設や譲渡・売却などを借主が自由できるなど、強い権利を有しているため基本的に地上権が設定されることはありません。
一方、賃借権では譲渡や賃貸などで土地の権利者(地主)も許可が必要になり、借地権のほとんどが賃借権となるのです。
地上権が、物や権利を直接支配できる「物権」の一種であり、賃借権は他の特定の人に対して特定の行為を請求できる「債権」という違いがあります。
ちなみに、同じように「他人の土地を使用する権利」としては、他にも次のような権利があります。
- 永小作権:小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜する権利
- 地役権:自分の土地の便益のために他人の土地を使用する権利
地役権は、公道に出るために隣地の一部を道路として使用するといったように、自分の土地を使用するために他人の土地を使う権利のことです。
永小作権も地役権もどちらも物権にあたります。
旧借地権と新借地権
借地権は契約が成立した期間によって「旧借地権」と「新借地権」の2つに分かれます。
それぞれ契約期限などが異なっており、どちらが適用されるかによって大きな違いがあるため、違いを理解することが大切です。
旧借地権とは
現在の借地権は、1992年に改正された借地借家法が定めた権利です。
それ以前に契約が成立した借地権は旧借地権となります。
新借地権が制定された今でも、旧借地権の時代に設定された借地権は旧借地権が適用されるのです。
また、旧借地権での期間が満了し更新する場合でも旧借地権が適用されます。
借地権を相続した場合などで、更新したからと言って新借地権が適用されるわけではないため、借地権の設定時期をしっかり把握しておく必要があるのです。
新借地権とは
借地借家法が制定された1992年8月1日以降に契約が成立した借地権は、新借地権が適用されます。
借地借家法ではそれまで借地人の権利が強かった点が見直され、借主・貸主の両方に不利益が出ないように改正されているのです。
また、借地借家法では、それまでの普通借地権に加えて新たに定期借地権が制定されました。
旧借地権と新借地権の違い
旧借地権は、一度貸してしまうと契約更新されることで土地が返ってこないと言われるほど借主の権利が強いものです。
一方、新借地権では期間満了時には土地が戻るように定められ貸主の権利も保たれるようになっています。
旧借地権と新借地権での大きな違いは、次の5つです。
- 存続期間
- 契約更新後の存続期間
- 老朽化した場合の取扱い
- 建物滅失時の再建築
- 地主の更新拒絶
なお、新借地権には普通借地権と定期借地権がありますが、ここでは普通借地権について見ていきます。
違いを一覧でまとめています。
| 旧借地権 | 新借地権 | |
| 存続期間 | 堅固建物:30年 非堅固建物:20年 | 30年 |
| 更新後の存続期間 | 堅固建物:30年 非堅固建物:20年 | 1回目:20年 2回目以降:10年 |
| 老朽化した場合 | 存続期間の定めがある場合:借地権は消滅しない 存続期間の定めがない場合:借地権が消滅 | 存続期間中の権利は保護 |
| 建物滅失時の再建築 | 借地期間が構造によって延長 | 再建築時に更新となる 地主の許可がなければ契約解除が可能 |
| 地主の更新拒絶 | 正当な事由がなければできない(正当事由が明確ではない) | 正当事由が明確に定義される 立ち退き料を払うことで拒絶も可能 |
借地権の種類

現在の借地借家法では、借地権は「普通借地権」と「定期借地権」の2種類に分かれます。
さらに、定期借地権は「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3つに分かれます。
| 存続期間 | 更新 | 契約書式 | 建物買取請求権 | ||
| 普通借地権 | 30年以上 | 1回目:20年 2回目以降:10年 | 定めなし | あり | |
| 定期借地権 | 一般定期借地権 | 50年以上 | 不可 | 書面で契約 | 特約で廃除可能 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 不可 | 定めなし | あり | |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 不可 | 公正証書で契約 | 30年以上年50年未満の違約時のみ特約で廃除可能 |
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
普通借地権
普通借地権は、旧借地権に基づいた借地権です。
契約期間が定められていますが、基本的には更新を前提とした借地権になります。
そのため、期間満了時に貸主は正当な理由がなければ契約更新を拒絶できません。
一方、定期借地権では更新ができないため、期間満了時に更地にして返還する必要があるのです。
定期借地権は、用途に応じて「一般借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」に分かれます。
一般定期借地権
契約の存続期間を50年以上に定め、建物の用途を問わない借地権です。
一般的借地権の場合、契約終了後に更新することはできず、建物の買取請求権も認められていないため更地にして返還する必要があります。
建物譲渡特約付借地権
期間終了後に、地主が建物を時価で買い取ることを最初から決めている契約です。
契約期間は30年以上となり、地主が建物を譲渡された時点で借地権が消滅します。
事業用定期借地権
店舗や商業施設と言った事業用の用途として土地を借りる契約の場合の借地権です。
用途が事業用の為、賃貸マンションといった居住用の建物では利用できません。
契約期間は10年以上50年未満となり、契約終了後は更地で返す必要があります。
また、事業用定期借地権のみ公正証書での契約が義務付けられているのです。
上記には上げていませんが、仮設工事やプレハブ倉庫と言った一時的な使用のための借地権である「一時使用目的の借地権」というものもあります。
借地権付き土地で家を建てるメリット
家を購入する際、土地を持っていない場合、土地を「購入する」か「借りる」という選択肢があります。
借地権付き土地であれば、一定の地代を払うだけで家を建てられるため土地の購入費用を大きく抑えられるというメリットがあるのです。
しかし、借りている土地のためデメリットもあります。
借地権付き土地を検討している場合は、メリット・デメリットを比較したうえで慎重に判断することが大切です。
ここでは、まず借地権付き土地に家を建てるメリットについて見ていきましょう。
メリットとしては、次の3つが挙げられます。
- 初期費用が安くなる
- 固定資産税や都市計画税の負担がない
- 利便性のよい場所に家を建てられるケースが多い
初期費用が安くなる
借地権付き土地は安く購入できるというメリットがあります。
通常土地を購入する場合「所有権」が売買されるものです。
しかし、借地権付き土地は借りる権利となるため、所有権の売買よりも価格が安く6~8割程度となります。
土地分の初期費用が安くなるため、その分家に予算を回すこともできるでしょう。
関連記事:【土地あり/土地なし】家を建てる費用の内訳を解説!
固定資産税や都市計画税の負担がない
借地権付き土地の所有者は、あくまで貸主(地主)です。
固定資産税・都市計画税は不動産の所有者に課せられる税金の為、借主に課せられることはありません。
固定資産税・都市計画税は毎年課せられる税金の為、負担がないのは大きな魅力と言えるでしょう。
ただし、負担がないのは土地についてのみです。
建物に課せられる固定資産税・都市計画税は、建物の所有者である借主の負担となる点は注意しましょう。
関連記事:持ち家にかかる固定資産税・都市計画税はいくら?計算方法を確認しておこう
利便性のよい場所に家を建てられるケースが多い
借地権付き土地の多くは利便性のよい場所というケースが多いものです。
「駅に近い」「商業施設が近い」といった生活に便利な場所で暮らせる可能性があります。
そのような条件の良い土地を購入するとなると、土地代が高くなるだけでなく、そもそも売りに出されていない場合がほとんどです。
利便性のよい土地を優先させたい場合、借地権付き土地も選択肢に入れることで理想を叶えやすくなるでしょう。
関連記事:都心と郊外住むならどっちがいい?メリット・デメリットや選び方のポイント
借地権付き土地で家を建てるデメリット
借地権付き土地にはデメリットも多いので、デメリットを理解しておく必要があります。
デメリットとしては、次の3つが挙げられます。
- 地代を支払う必要がある
- 将来的に土地を返還する必要がある
- 建物の売却や増改築に地主の承諾が必要なケースがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
地代を支払う必要がある
借地権付き土地を購入した後も、毎月地代を支払うことになります。
地代は、土地の立地や面積によっても大きく異なりますが、定期借地権の場合おおよそ土地価格の2~3%程が目安です。
住宅ローンの返済に加えて、毎月数万円程の地代も支払わなければならない点に注意して資金計画を立てる必要があります。
固定資産税や土地購入費用を抑えられても、毎月の地代がかかることからトータルでは費用が大きくなる可能性もあるでしょう。
契約更新時に更新料がかかるケースや、地価が上がれば地代が値上げされる可能性もあります。
また、購入時に住宅ローンが組めない可能性があることにも注意が必要です。
金融機関によっては、借地権付きの物件に制限を設けているケースも珍しくないため、事前に利用を検討している金融機関の条件をチェックするようにしましょう。
将来的に土地を返還する必要がある
借地権付き土地は、契約更新することで長期的に住むことが可能です。
しかし、契約更新しない場合、契約期間終了後には土地を返還しなければなりません。
返還する際には建物を解体して更地にして返還することが原則となり、解体費用は借主の負担となります。
ただし、普通借地権の場合、建物の資産価値がある場合などは地主に買い取ってもらえる可能性もあります。
とはいえ、契約時に特約で買取請求権を排除している場合や契約期間中に地代の滞納がある場合などは、買取請求が拒絶される可能性もあるので注意しましょう。
契約を更新すれば、そのまま住み続けられますが、更新料を求められるケースも珍しくありません。
また、更新したくても地主の要望で立ち退きを求められる可能性もゼロではないのです。
あくまで土地の所有権は地主にあるので、地主との関係性によってはトラブルに発展するケースがある点に注意し、良好な関係が築けるように心がけましょう。
建物の売却や増改築に地主の承諾が必要なケースがある
借地権には地上権と貸借権の2つがあり、貸借権で契約している場合、建物の売却・譲渡や増改築を地主に無断でできません。
売却や増改築しようと思ったら地主に承諾を得る必要があり、場合によっては承諾料を要求される可能性もあるでしょう。
将来的に「家を売却したい」「子供に家を渡したい」「二世帯住宅に増改築したい」となった場合にトラブルに発展するケースもあります。
ただし、増改築は規模によっては承諾なしでできる場合もあります。
どの規模は承諾が必要で、どこまで承諾なしでできるかは契約時にしっかりと確認しておくことが大切です。
まとめ
借地権について、概要や種類、借地権付き土地で家を建てるメリット・デメリットなど解説しました。
借地権付き土地で家を建てるのにはさまざまなメリットがありますが、一方で注意しなければならないこともあります。
借地権付き土地で家を建てる際には、より一層、知識や経験の豊富な住宅会社で家を建てることが大切になるでしょう。
タクトホームではこれまで59,000棟の戸建住宅を施工。
さまざまな状況に応じた家づくりをサポートしています。
借地権付きの土地に興味を持っている方や不安に感じている方など、ぜひ一度ご相談なさってみてはいかがでしょうか。